
Sapporo International
Communication Plaza FoundationInternational Community Bureau




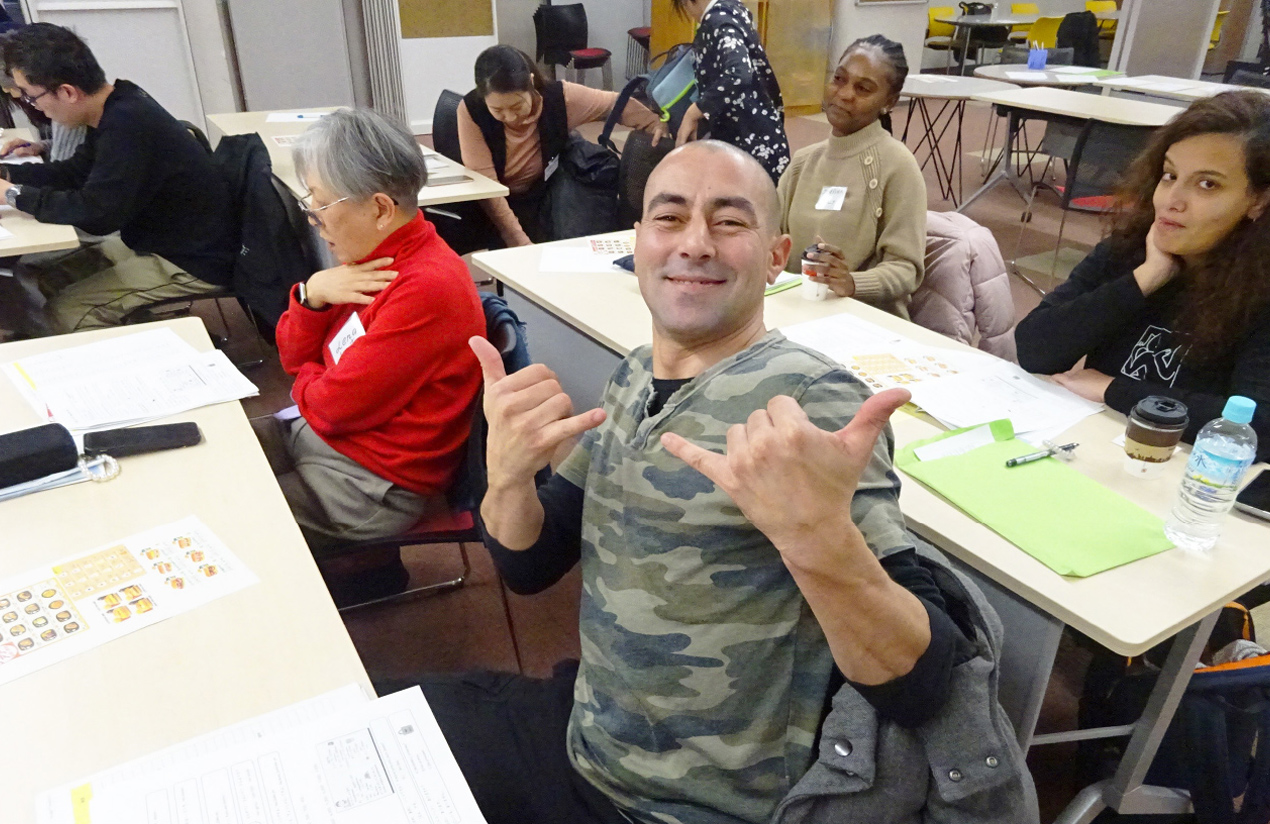
Latest News
一覧を見る-
2025.06.30
「SAPPOROこども未来トーク2025」に参加する小学6年生を募集します!
-
2025.06.23
熱中症に気を付けましょう!
-
2025.06.13
札幌市・大田広域市 姉妹都市提携15周年記念友好音楽会のご案内
-
2025.06.10
「SAPPOROこども未来トーク2025」大学生サポーターの募集
-
2025.06.04
ホームステイボランティア説明会 ~家族で楽しむ国際交流~(6/14)
-
2025.05.30
【申込受付中】札幌-ポートランド姉妹都市交流事 Let’s Talk English 高校生スペシャル2025 🗽(7/7)
-
2025.05.26
🌸さっぽろフラワーカーペットに参加してみませんか🌸
-
2025.05.16
【申込受付開始】外国人のための無料専門家相談会(6.21)
-
2025.05.13
【募集開始】多文化共生事業助成金について


